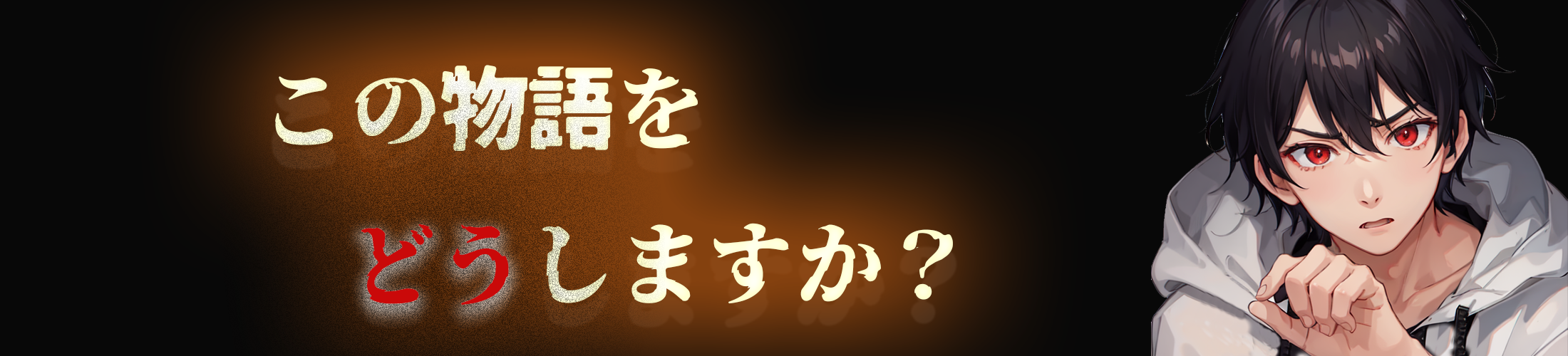「行くとしよう」
その看板は夜の街によく似合うカラフルなネオンで彩られていた。
『BAR 無法のカクテル』

西部劇に出てくる店にありそうな押込式の扉を両手で押し開け――店に入る。
……やれやれ、ちょいとやかましいな。かかってる音楽もあまり”粋”じゃない。
派手で煽るためだけに奏でられているような曲調。
おいおい、ポールダンサーまでいるのか。
艶かしく棒に絡みつく肢体。
こりゃあレコードには見せられない。
あまり目を向けないほうが良さそうだ。
ただ……チラッと見た時に……踊っている子がやけに若いように見えて、少し気になった。

……とにかく総じてガラは悪い。
そして……どうやらそれに見合った客層のようだった。
入って来た私に対する無遠慮な視線と嘲笑。
しかも、チラホラ人間離れしている。象にしか見えない顔つきの者。肌が紫の者。テーブルの上でニタニタ笑ってる小人のアレも……どうやら人形ではないようだ。
【わぁ……朝なのに、こんなお店やってるんだ……】
……朝?今は深夜のはずだし、さっき夜空が見えていたはずだが……まぁ、よく見てなかったのかもしれないし、ここは屋内だ。
勘違いしたのか。いや……だとしたら、彼女は時間感覚が無くなる場所にいるという事か?
――今は追及してる場合でもないな。
カウンターに向かうと、グラスを磨いていた店主らしき老人に私は話しかけた。
「八神改だ。依頼人はアンタだろ?来たよ。VIPルームに通してもらおうか」
【……え?】
眉間に刻まれた深いシワ、傷だらけの手。生え放題に見えて、キチンと手入れされているヒゲに、スキなく着こなされたYシャツ。
その目つきの鋭さから察するに、わりとハードな人生を送ってきたんだろうか。
そういった気骨のありそうなじいさんは嫌いじゃない。
「まさか、本当にこんな世界に入れるとは思ってなかったけどね。アンタから事務所に届いた手紙の内容は……まぁ正直ゾクゾクした。文才あるじゃないか、じーさん。
アンタが手紙の差出人、モーリなんだろう?」
「あぁ、自分がモーリだ」

「私を選んだ理由は?」
「……ふざけた口調でヘラヘラした男という評判だが……子供が絡む事件にだけは目の色を変えると聞いた」
「どこで聞いたんだが知らんが、まぁそんな気分の時はあるかもね」
「感謝する。……案内しよう。ついてきてくれ」
「分かった。あぁ、1つだけ注意事項だ。私は独り言が好きでね。しかもやたら説明調な独り言をしたがるんだ。それは勘弁してほしい」
「……かまわんよ。その程度ならこちらの世界ではマトモな部類だ」
そう言ってじいさんはカウンターから出ると、手招きをして店の奥へと歩き出す。
丸テーブルがいくつも並んだ店内の奥にカーテンで仕切られている空間があった。
ちょうど踊り子達のステージを真横から見れる位置に……どうやら特等席みたいなものが存在しているらしい。
「……との事なんで……遠慮なく独り言を再開すると……私がこの25時の世界に来たのは、見ての通りこのご老人から依頼を受けたからなのさ」