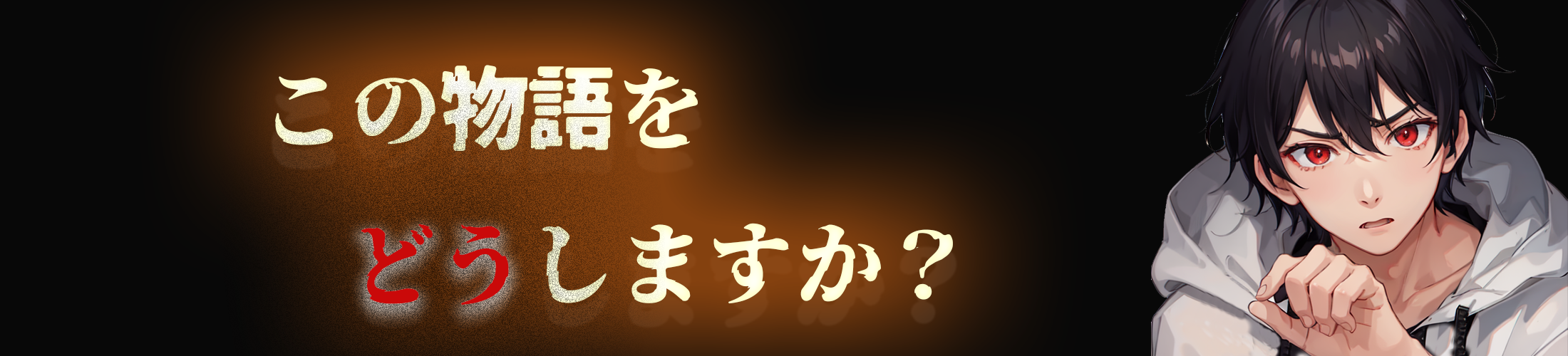少女はつっかえているものをノドから頑張って取り出すようにしながら……言葉を紡いだ。
「モーリは……猫が……嫌いだって……でも……お腹をすかせている猫が……かわいそうで……だから……」
「ホラくだらない理由だ!それにどんな理由であっても――」
「お前の評価基準は間違っている。計算方法も」
イルヴィーの声をさえぎり、私は言った。
「確かに子供はよく間違える。ろくでもないガキも多いさ。私もそうだった。
でも――無理もないのさ。まだ知らない事が多いんだ。
自分の言葉がどれだけ他人を傷つけるのかも。自分がどれほど大事に思われているのかも」
気づくまでには多くの時間と失敗が必要だ。……私もそうだった。
「それらは経験しながら学んでいくんだ。自分が大人になって、苦労しながら他人とつきあって――そしていつか――自分の足下に頼りない力でしがみつく小さな……小さな存在をたまらなく愛しいと思うようになって――はじめて気づいていく事なのさ」
私はかがみこみ、少女の首輪にそっと触れる。
「そして子供はたくさんの悪い事をしながらも、それより多くのものをくれる。
その子が笑うだけで――元気に走り回っているだけで――フワフワの毛布やストーブよりあったかいものが胸にこみあげてくる。
それに比べたら多少の罪なんて帳消しになるくらいにね」
「…………」
マリと呼ばれた少女の瞳にかすかな光が戻る。
その頭をなでながら私は言った。
「探偵アラタが教えよう。罪は”赦す”事もできるんだ。とりあえず私は赦すよ。
猫のために牛乳盗んだ?なんだそりゃ?私ならもっと持って行けって言うねぇ。
――で、あんたはどうなんだい?モーリ!この子の事を赦すかい?」
「赦す……」
モーリは声を震わせながらそう言った。
「マリ……まさかそんな……そんな事のために……赦す……赦すとも」
その時、不思議な事が起きた。
少女の首に下げられていた札に書かれていた「咎」という文字。それが……すーっと消えていく。
カシャン……
さらに――あっけない音をたてながら少女の自由を奪っていた首輪と鎖がまるで飴細工のように崩れ落ちた。
「モーリ!……モーリ!!」
少女がモーリの元へと走る。モーリはしっかりとその体を抱きとめた。
【……すごい……】
「ロォォォオオオオオオッッック!!!」
不意にイルヴィーが叫ぶ。
なんでいきなり酒の注文を?と思ったが、どうやらそれは違うようだった。
奥にあったドアが不意に弾け飛び……ドアのサイズより2倍は大きいものが無理矢理部屋に押し入ってくる。
「はい……イルヴィー様……オデを……お呼びで……」