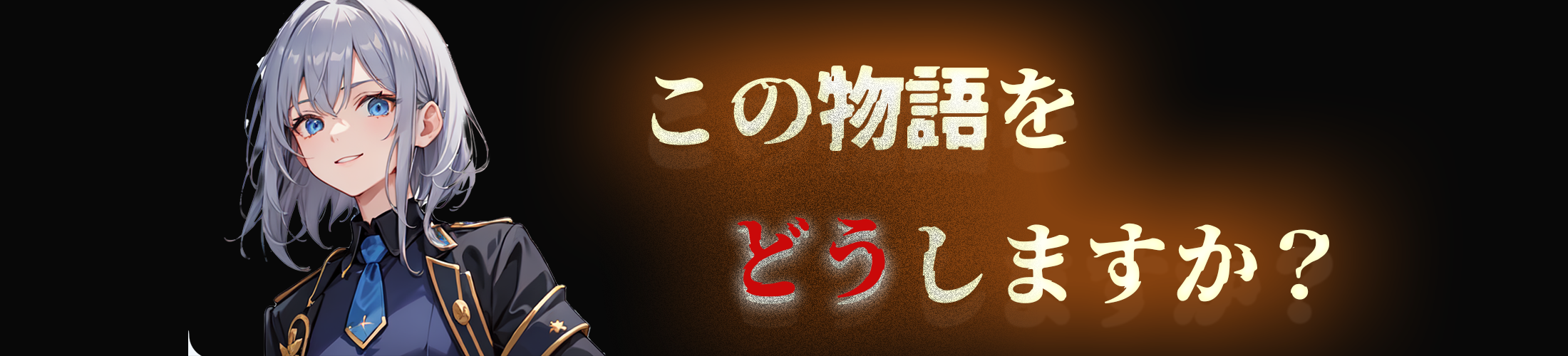そのルールの中で怒ったり反抗して見せたって無益でしかない。
それくらい会って間もない私ですらすぐに分かりましたよ」
「あら素敵。流石探偵ってところかしら」
イルヴィーの鼻がまたヒクつく。
私は手にしたグラスを掲げ、うやうやしく近づき、イルヴィーの持つグラスに合わせて『乾杯』の礼を取る。
「おほめいただきありがとうございます。探偵にとって一番の喜びは自分の調査した事実や推理を依頼人に聞いていただく事でしてね。
ついでながらもう一つ披露してもよろしいでしょうか?」
「ぜひうかがいたいわ」
「では――探偵アラタがお教えしよう」
私はニッコリとイルヴィーに微笑みかけ――そして右の拳を思い切りその鼻っ面へと叩きつけた。
「――ぶへぇっ!?」イルヴィーがソファーごと後ろへと倒れる。
「――ゲスと飲む酒はマズい。クソ以下の味がするね。重罪だ馬鹿野郎」
【……やっぱり、とりあえず殴っちゃうんだ……】
あぁ、とりあえずスッキリするしね。
「き、きひゃま……死にたいのか……」
「私が必要なんじゃないのかい?これは推理だが――アンタは人の失敗を見つけ出して罪人に仕立て上げる事が得意なようだ。それが”役”を奪うって事かい?」
催眠術なのか魔法なのかよく分からんが……まぁ、似たような事をするゲスは私の世界にもいる。
「でも、その一方で誰かに新しい”役”を与えたりする事はできないんだろう。
だから私を呼んだんだ」
イルヴィーは手で顔をおさえて、こちらを睨んでいたが――甲高い耳障りな笑い声を上げた。
「あぁ――なんだ、てめぇ、ただの馬鹿か。その程度の理屈でこのイルヴィー様の上に立てると思ったのか?
そんなもの――ここでお前を殺してまた次にやり直したらいい。
だが……この不愉快さはもうそれだけではおさまらないわね。
お前を殺した後にお前を連れてきた罪をそこのじじいとガキにも払ってもらう!罪の上塗りね!!」
「ありゃ……そうなるのか。それは少し読み違いだった」
【ちょ、ちょっと……】
「しかし……罪……罪ねぇ……それも少し私には分からないんだなぁ。そもそもこんな可愛らしい少女が一体どんな大それた罪を犯したっていうんだい?」
私は立ちつくす少女に向き直る。艶めく黒髪。浅黒い肌に黒真珠のような大きな瞳。私の世界にいたなら中学生くらいだろうか。
とても純朴そうな女の子に見える。私が普段街で見かける不良娘のほうがよっぽどイケナイ事をしてそうだ。
「……はっ!そのガキは盗みを働いたのさ!よりにもよって自分を大事に育てて養ってくれているジジイの家からね!牛乳を盗んだ!何度も!
恩知らずにもほどがあるよ!重罪さ!!」
ビクッと少女が震える。その焦点の合っていない瞳から……大粒の涙がこぼれた。
「――何のために?」
「あぁ?」
「お前には訊いてない。私はマリと呼ばれたこの子に訊いているんだ。ねぇ……君、どうしてそんな事をしたのかな?
良かったら……教えてくれないか?……ここにいるモーリのために」
「……猫が……」