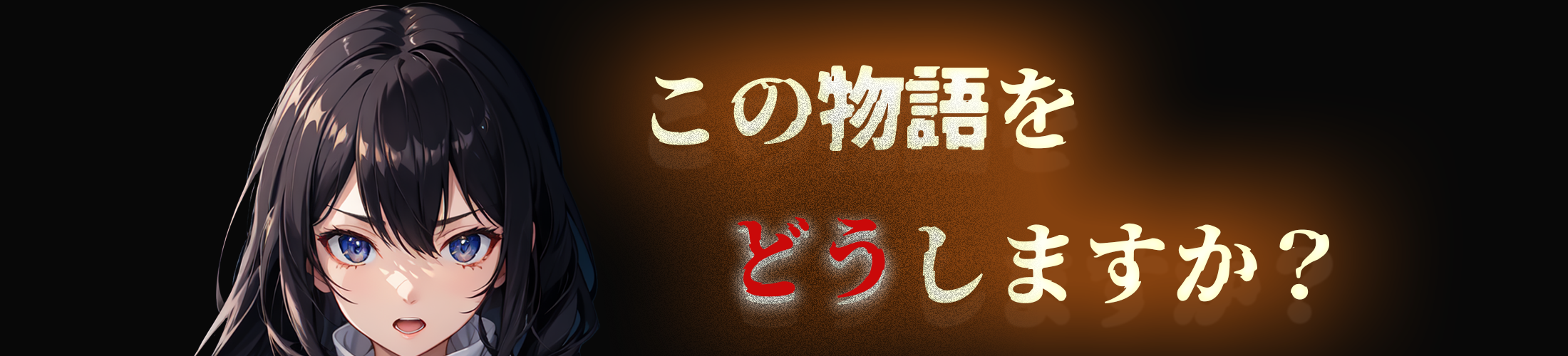「しばらくここで凍っててもらおうかな?仮にもラスボスって話なんだし凍ったくらいで死なないよね?」
そして、手をかざしーー氷結を意味する古代語と何か契約されたキーワードを口にするとーーハンターの周囲に巨大な氷柱が出現し、その身体を一瞬で凍結させたようだった。
「うっぎゃ……さ、寒いっっ!ちょーー魔法ってチートすぎっしょーーっ!」
床に手をついたままの少女が悲鳴を上げる。
確かにあの下半身では寒そうだが……まだ生命に別状はないだろう。
それよりも……今、あの凍りついたハンターにこの拳を叩きつけて砕けば……それで全てを終わりにできるのではないのか。
「く……っ……なぜ、動かない……」
なぜなのか。俺の身体はハンターに向かおうとしない。
その俺の様子を見てモーリが小声で声をかけてきた。
「どうした?」
「――分からない。あのハンターに向かおうとすると……身体が原因不明の不調を起こして動かなくなるようだ」
「そうか。では――あっちに行くのはどうだ?」
そう言ってモーリが指さしたのは……部屋の片隅で先ほどから叫び声を上げている四つん這いの少女のようだった。
足が……動く?確かに、あちらに向かおうとする分には何ら異常なく身体は動くようだった。
「……なぜだ……」
「すまんな。マリに年の近い少女を見るとやはり放っておけん。だが……自分ではあの子を助けてはやれないだろう」
その質問をしたつもりはなかったが、特に訂正や説明が必要な場面でも無いようだった。
やむを得ない。あの少女は人類の繁栄に貢献しうる。ならば、助けよう。
力がみなぎっているこの身体は――ただの一飛びで少女の元へ到達した。
「――ライダ――キィィイイイッツク!!」
「きゃあああああっ!?ちょ――何するのーっ!?」
「蹴りだ」
短く少女に伝え、少女の周りを覆っていた重力結界ごと床を蹴り砕く。
「わ――ちょ――っ!」
「動かないでくれ」
そのまま少女を片手に抱き、俺は壁を蹴ってモーリのそばへと駆け戻る。
「ふーん?そのおねーさんを助けて2対1にしようって事かな?」
余裕たっぷりに転生鳴浪は笑った。だが、間違えている。
「それは違う。現状の正しい構図は2対1対1という事になるだろう」
「……ん?そのおじいさんもやる気って事かな?」
モーリが一瞬目を見開いたが、モーリより先に俺が「それも違う」と否定する。
「そのハンターは凍っていない。目に意識を集中させて確認した。凍っているのは表面上だけのようだ」
「……え?まさか。だって――」