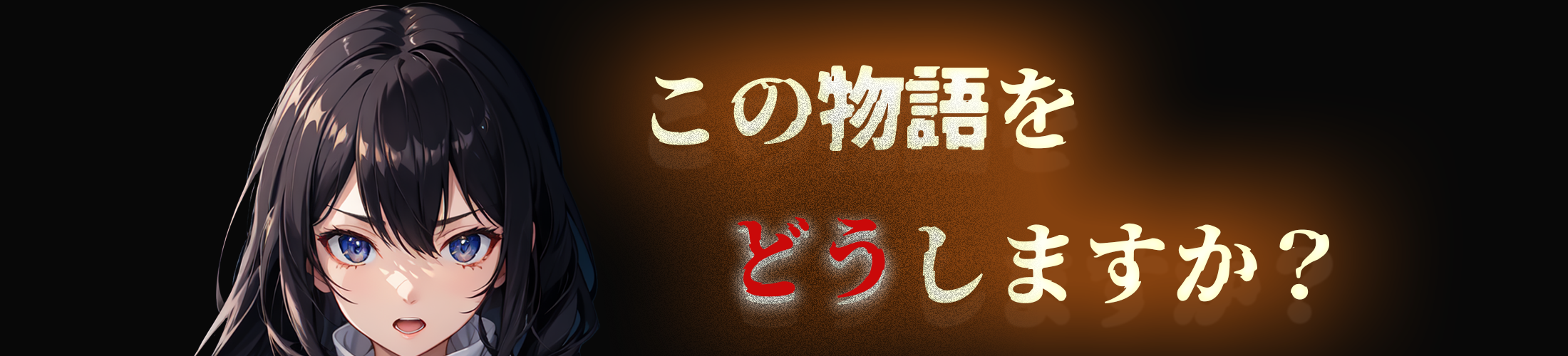【……ひひ……ずいぶん楽しそうにお喋りしてるじゃないか、ボイスぅぅ……】
その声がイヤホンから届き、僕は無意識に眉をしかめたのだろう。
【そんなに嫌そうな顔すんナヨ。直に傷つくゼ?エンドちゃんだよーん】
僕達担当者の様子は全てこの声の主……エンドと名乗る彼女が把握している。
これは担当者達の中で僕しか知らない事だ。
「……これ。今僕が喋っても大丈夫なんですよね?」
【そりゃもちろん。他のみんなに内緒で個別回線を繋げてるんダヨ。ちゃんと言ったろ?お前には特別扱いしてやるって】
「どうも。それが心配だったのと……後はちょっと……あまりにも違う声のトーンでいきなり来られたからびっくりしたんですよ」
僕は机の上のモニターを見る、ちょうど画面はモニタリングが切り替わり……次は雷田雄大のモニタリングになったようだった。
モニタリングの様子を見る限り、確かにエコーにも雷田雄大にもこのやり取りは聞こえていないようだ。
【この声も、お前だけに聴かせてる声ダヨ。可愛い女の子と二人だけで秘密の会話ができて楽しいだろぉ……?くっくっく!】
「いえ……僕、そういうの興味ないので」
努めて感情を込めずにそう伝えると、相手はさらに笑ったようだった。
【つれないねぇ。ま……そういうところがボイスっぽいなーって思って、お前をボイスにしたんだけど】
……それは……どういう意味だろう?
「ボイスっぽい……って……もしかして、僕の前にもボイスって名前を付けられた人がいたって事ですか?」
【察しも良い子だね。そうダヨ。このアホみたいな実験は過去にも行なわれたのサ。2回やって2回とも失敗したけどね。で……今回こそは成功させたいってんで、前回の実験でわりと上手くいってた部分はあまり変えずにやり直そうって話になったワケ」
「そうですか」
【んん?気にならない?この話?】
「特には。僕の一番の関心事はこれがいつ終わっていつ帰れるかって事だけですし」
【くっくっく!それは直にケッコウ!なんだかあの連中と仲良くなってきたみたいだからてっきり心変わりを――】
「馬鹿馬鹿しい」
僕は真っすぐに画面を見ながら言った。
その独り言が狭い壁に反響する。薄暗いネットカフェのような個室で、こんな会話……ただでさえ憂鬱な気分がさらに暗くなる。
「心の底から本音で思ってますよ。くだらないから早く終われ……って」
【直にいいねぇ。じゃあ……そろそろアタシももう少し積極的に動く事にしようかなー】
「そんな事できるんですか」
少し驚いて僕はそう言った。
この実験にはなんだか小難しいルールが色々とあり、相当なお金をかけられた設備の中で僕らはコレをさせられている。
この事からもかなり大きな組織が実施しているんだろうと僕は思っていた。
……だからエンドもその組織の歯車として……勝手には動けないから裏でコソコソとこんな事をしているんだと思っていたんだけど。
【んー?できるサ。こー見えても……って今は見えないか、わはは!アタシはこれでもかなり重要なポジションの存在なんダヨ。お子ちゃまボイス君にも分かりやすく言うと、えらーい地位にいるのサ!」
「中間管理職以上の役職って事ですか」
【可愛くない返しだね。くっくっく……でも、まぁそういう事。だからアタシは色んな権限を持っている。そしてこの実験をどう動かすかも……ある程度アタシが決めていい事になっているのサ】
「なら……できるだけ早く終わる方向性でお願いします。コメントもほとんど来ないし、僕にはこの実験の意味がよく分からない」
まぁ……その分、僕たちのやる事は少なくてすむって話なわけだが。
ただ画面を見ているだけでイスに座りっぱなしというのも、それはそれで辛い仕事だ。
【前回もそうだった。けど、最終的に大騒ぎになったらしいけどね。まぁ、こんなよく分からない奇妙なシロモノに進んでコメントしようって奴もなかなかいないのサ!くっくっく!】
「はぁ……」
【ただ……ボイス君には悪いけど……どっちにしても、もう少し盛り上げたいナーとかは思うワケよ。もっとぐっちゃぐちゃにしてあげたいナーとか。だって――ホラ――なんか、ムカつくじゃん?】
そのエンドの声には……何か……黒く塗りつぶされた怨念のようなものがこもっている気がして……僕は思わずぞっとした。
でも――
「まぁ……お任せします」
とだけ、僕は伝える。
僕の目の前にエンドが突然現れた時から彼女に感じていた――深く、暗い、何か。
でも、だからこそ僕は彼女の言葉に従う事にした。
それは……同じく暗い衝動を持つ僕に……必要なものだと感じたから。
彼女の目的が何であれ……僕が必要としてる”力”をくれるなら何だっていい。
「僕は僕の目的さえ達成できるなら何でもいいし、言われた通りに従います」
【良い子だボイスぅ……お前がもうちょっと大きかったらエロい事もさせてあげたけどなぁ……ひっひひひっ!!】
「だから……僕、そういうの興味ないですから」
【それは残念。分かってるヨ。お前が憎くて憎くて仕方ないあの悪ガキ共を、アタシがアリのように踏みつぶしてやればいいんだよなぁ?】
「そうです」
――そうだ――それこそが僕の目的だ。だからこんなよく分からない実験なんてどうだっていい。
「アタシは約束は守る。会った時に、それができるくらいの権力は持ってるって証明したダロ?」
「……逆らったら何されるか分からないっていう事も把握しましたよ」
「いやーん。アタシが可愛いボイス君にそんなひどい事するわけないだろぉ?直に傷ついちゃうゾ?」
「とにかく……僕は、期待、してます。あなたに」
「……くっくっく!やっぱりいいなぁお前は。ひっひっひ!もう少し楽しくお喋りしたいとこだけど……まぁ今回はこれくらいにしとこうか」
彼女の笑い声には……何かに対する憎悪と悪意が常にこびりついている。靴の裏に付いて離れないガムのように。
ひとしきり低く笑った後、彼女が「マタナ」とだけ告げる。
「――はい」
回線が切れるブツッという微かな音を聴いてから……僕は、少し……少しだけ、深く息を吐いた。